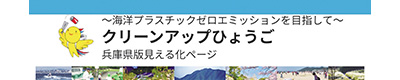ここから本文です。
五国の現場から -SCENES OF GOKOKU-
|
県内各地で行っている県の主要施策の取り組みなどをクローズアップします |
地球温暖化により始まった研究開発から9年
新品種米「コ・ノ・ホ・シ」とは
県内産の米は近年、夏の高温の影響で白く濁るなど、品質低下が問題となっていました。県とJAグループ兵庫は2016(平成28)年から暑さに強い品種の開発に取り組み、9年がかりで新品種「コ・ノ・ホ・シ」が誕生しました。今年から本格的に生産が始まったことを受け、齋藤元彦知事が開発者と試験栽培に協力した南あわじ市の生産者にこれまでの道のりを聞きました。

兵庫県が独自の品種を開発したのは何年ぶりですか。
篠木 20年ぶりです。一般的に米の品種開発には14年が必要とされていますが、生産者やJAグループ兵庫から「できるだけ早く」との要望を受け、コ・ノ・ホ・シは9年で開発しました。
齋藤 どうやって5年も短縮できたのですか。
篠木 ガラス温室を整備し、冬場も稲を作るようにしたのが一番の要因です。さまざまな品種を交配して1万系統を作り、そこから食味試験や現地試験などを重ねて絞り込んでいきました。
|
ガラス温室で育つ稲。 |
齋藤 試験栽培で良質の米ができたと聞きました。
神田さん そうなんです。南あわじ市内の稲作面積は年々減少しています。高齢化もありますが、高温障害の影響で品質の低い米が増えると収益が上がらず、米から離れる生産者もいます。コ・ノ・ホ・シは従来の栽培方法で、ぴかぴかのきれいな米ができます。主力品種のキヌヒカリから切り替えることで、品質が上がると大いに期待しています。
開発中の苦労は。
篠木 温室の温度管理には特に気を使いました。暑さに強い品種にするため、夏場でも涼しい日は暖房を入れて高温障害が出やすい27℃以上を保つようにしました。
齋藤 本格的に栽培が始まったことで、緊張状態から解放されたのでは。
篠木 まだですね。生産者の「いい米ができた」という声と、消費者の「おいしい」という声を聞いて初めて実感が湧くと思います。
神田さん 1万系統から選抜したという苦労を知り、失敗は許されないと思いました。初めて試験栽培をした時、キヌヒカリと比べて葉の色が薄かったので不安になりましたが、巡回に訪れた篠木さんから「順調ですね」と声をかけられて安堵(あんど)したのを覚えています。
コ・ノ・ホ・シの魅力は。
神田さん キヌヒカリの作り方と同じなのに暑さに強いことと、甘みがあっておいしいことです。
齋藤 お二人のコ・ノ・ホ・シに対する思いがひしひしと伝わってきました。県民の皆さんに安心して届けられる持続可能な米になることを期待しています。
 |
篠木佑 【県立農林水産技術総合センター主任研究員】 開発リーダー。9年間で新品種を開発する計画を立て、遂行。 |
 |
神田智彦さん 【JAあわじ島営農部長】 JA勤務の傍ら、南あわじ市内で営農。新品種の現地試験に携わる。 |
 |
齋藤元彦 【兵庫県知事】 |
| 進行 | 清水理恵子 【県広報専門員】 |
コ・ノ・ホ・シとは
主に県南部で栽培されているキヌヒカリと同じ極早生(わせ)でも、高温に強いのが特徴。今年は県内の150haで栽培し、来年は1,500ha、再来年は4,500haへと段階的に拡大する予定です。 |
「コ・ノ・ホ・シ」の新米(1kg)を3人にプレゼント
応募方法はプレゼントクイズのページへ
〇現地での様子は、県民情報番組「ひょうご発信!」のアーカイブ(7月27日放送)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)で視聴できます。

お問い合わせ